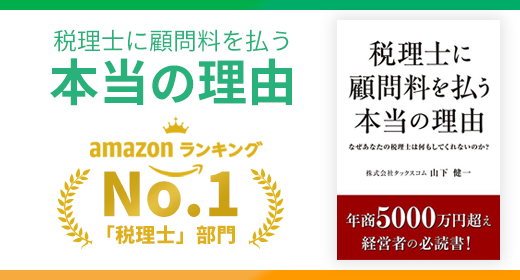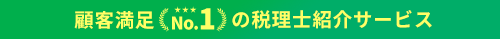【起業前に知るべきこと】個人事業主が納めるべき「事業税」

個人事業主やフリーランスの方が支払うべき税金のひとつに、「事業税」があります。しかし、個人事業主であれば、経費として処理することもできる税金もあります。
また、この事業税は、納めなければならない業種や条件決められています。この記事では、個人事業主で事業税を納める必要がある業種や事業税の計算方法などについて解説していきます。
目次
個人事業主が納めるべき2種類の税金「租税公課」と「事業主貸」
個人事業主が納めるべき税金には、「租税公課」と「事業主貸」の2種類の税金があります。
・租税公課
租税公課は、事業そのものにかかる税金です。事業を運営していく上で欠かせないコストなので、「租税公課」という勘定科目で経費として計上することができます。租税公課として経費に計上することが可能な税金には、個人事業税、消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、会費などがあります。
・事業主貸
事業主貸とは、事業ではなく、個人事業主の個人にかかる税金です。事業とは関係ないので、経費として処理することはできません。経理上では、「事業主貸」という勘定科目で計上されます。事業主貸として経費にすることができない税金には、所得税、相続税、都道県民税、市町村税、住民税、国税や地方税の延滞金や加算金、罰金などが代表的なものとして挙げられます。
個人事業税とは?
個人事業主が事業として納め、経費として計上できる「租税公課」のひとつが、「個人事業税」です。個人事業税は、個人で事業を営むと決められた業種に対して課されている税金です。
事業税は、地方税のひとつで、都道府県に対して納付します。つまり、事業で得た所得を国に納める税金が「所得税」で、都道府県に納めるのが「事業税」と「住民税」となっています。
ただし、事業税の場合は、対象となる業種が決められていたり、控除額が所得税と異なったりしているため、事業税が課税されない個人事業主もいます。では、事業税が課されている業種には、どのようなものがあるのでしょうか?
個人事業税を納めるべき対象者とは?
個人事業税を納めるべき対象者は、次の条件をすべて満たしてるなら課税の対象となります。
①事務所や事業所がある
個人事業税は住所ではなく、事務所や事業所の所在地の都道府県で申告と納税をすることが定められています。
②所得金額が290万円超えている
個人事業税は、事業主控除として290万円を差し引いて算出します。そのため、所得金額が290万円以下の場合は、事業税が課されることはありません。
③法律で決められた70の業種に該当している
個人事業主の中で、事業税が課されているのは、法律で決められている70種類の業種のみです。この業種に該当しない個人事業主は、事業税を支払う必要はありません。70の業種は3つの区分に分類されており、それぞれの区分ごとに3~5%の税率が決まっています。法定業種ごとの分類は、次のようになっています。
・第1種事業(37業種):税率5%
物販販売業、保険業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出発業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂など)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
・第2種事業(3業種):税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
・第3種事業(30業種):税率5%
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、経理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、測量士業、土地家屋調査士業、海自代理士業、印刷製版業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に関する事業、装蹄師業
このように70種類の業種をみてみると、ほとんどの個人事業主は該当していると言えるかもしれません。基本的にほとんどの業種が課税対象となっていますが、この法定業種70種類に含まれていない業種は、事業税は課されません。例えば、農業、スポーツ選手、芸能人、音楽家、漫画家、小説家などが挙げられます。
参照:東京都主税局「個人事業税」
個人事業税の申告は必要?
個人事業主として、所得税の確定申告をしているのであれば、個人事業税の申告手続きをする必要はありません。「確定申告書B」の下部に、事業税に関しての欄が設けられています。そこに該当項目を記入するだけで大丈夫です。
ただし、所得税の確定申告をした後に事業を廃止、もしくは廃業した場合は、1ヶ月以内に個人事業税の申告をする必要があります。なお、死亡による廃止の場合は、死亡した日付から4ヶ月以内が、個人事業税の申告期限となります。
個人事業税の納付時期について
個人事業税の納付は、毎年8月になると、各都道府県から個人事業税の納付書が届きます。個人事業税が1万円以下の場合は、8月に一括での支払いとなります。
1万円を超える場合は、8月と11月の2期に分割しての納付が可能です。納付期限日が土日祝と重なる場合は、翌平日が期限日となります。振替の場合は、それぞれの納付期限日が振替日になります。2021年度の納付期限日は、次のようになっています。
・個人事業税の2021年の納付期可
第一期分:2021年8月31日(火)
第二期分:2021年11月30日(火)
なお、初めて事業税を納税する場合、事業所得が290万円を超えて納税することになっていても、8月中に納税通知書が送られてこないことがあります。なぜなら、納税通知書は、毎年個人事業税を納めている個人事業主から優先的に送付しているからです。
そのため、初めての納税者は、後回しにされる傾向があるようです。しかし、送付が遅れているとしても、必ず送付されます。もし9月以降に送付されたとしても、納付期限日も変更されているので、特に心配する必要はありません。
個人事業税の納付方法について
納付する場所は、市区町村の役所や税事務所、郵便局、銀行などで行えます。また、口座振替にしたり、30万円以内であれば、コンビニエンスストアでも納付することが可能です。さらに、必要な手続きをするなら、クレジットカード払いにすることもできます。
個人事業税の計算方法について
課税対象の業種に該当する場合、個人事業税の税額は、
「所得金額=収入金額-必要経費-青色申告特別控除金額」
「課税所得金額=所得金額+青色申告特別控除金額-事業主控除額(290万円)」
「個人事業税の税額=課税所得金額×事業税率」
という3段階の算式で、算出します。
事業税は、所得税や住民税などの計算方法とは異なり、青色申告特別控除の金額を差し引くことができないため、課税所得金額を計算する際に、足し戻す必要があるので注意しましょう。
なお、個人事業税では、青色申告特別控除は適用されませんが、「事業主控除」と「繰越控除」は適用されます。「事業主控除」は上記でも少し触れましたが、1年間事業を行っているなら290万円、すべての事業主が一律で差引けます。もし1年を満たない場合は、事業を行った月数分だけ控除されます。例えば半年間しか事業をしていないのであれば、6ヶ月分の145万円が適用されます。
また、「繰越控除」とは、その名前の通り、その年に控除しきれなかった金額を翌年以降に繰り返すことが可能です。例えば、所得が赤字だったとき(青色申告のみ)、災害で事業用資産が損失したとき(白色申告のみ)、資産の譲渡で損失が発生したとき(青色申告のみ)などの場合に、繰越控除が適用されます。
個人事業税は減免措置がある
個人事業税は、期限までに申請すれば、減免してもらえるケースもあります。例えば、次のようなケースに該当する場合、個人事業税を減免してもらえるかもしれません。
・地震や洪水などの自然災害の被害を被った場合
・生活保護を受けている場合
・自分や生計を同一している配偶者や親族等の高額な医療費を支払った場合
・本人や扶養する家族が障害者の場合
減免するためには、納税者本人が納付期限までに申請することが求められています。なるべく早めに都道府県の税事務所へ行き、相談されることをおすすめします。
個人事業税の仕訳方法について
個人事業税の納税額は、個人事業の経費として計上できますので、「租税公課」という勘定科目を使って帳簿を記帳することができます。次のように帳簿をづけをします。
例:〇月〇日 (借方)租税公課100,000 (貸方)現金100,000 摘要/個人事業税の納付
このように個人事業主が納める税金の中には、経費に計上できる税金もありますので、計上できるものは忘れずに記帳するようにしましょう。
個人事業主が支払うべき税金と納付時期のまとめ
個人事業主には、「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」を支払うべき義務があります。その中でも「個人事業税」は納付が一番遅い税金です。では最後に、個人事業主に課せられている各種税金の納付期限の流れを確認してしましょう。
所得税
納付期限:確定申告期限日まで
消費税は原則、確定申告期限日までに納付しなければいけません。つまり、各艇申告書の提出期限と納付期限は同じです。通常、確定申告期限日は3月15日ですが、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で4月15日まで期限が延長されました。個人事業主本人が納税額を計算し、納付します。
消費税
納付期限:3月31日まで
所得税の納付が終わったら、消費税の納付です。消費税の場合、改行してから2年間は納付義務は発生しません。また、開業してから2年以上経過している場合でも、前々年の課税売上高が1,000万円以下であるなら納付は不要です。
住民税
納付期限:6月30日・8月31日・10月31日・翌年1月31日の4回で分納
住民税は地方税です。税務署に確定申告をすると、その情報が各地方自治体に伝達され、6月上旬~中旬頃にかけて住民税の通知書が地方自治体から届きます。住民税は4回に分けて納付することができますが、一括で納付することも可能です。その場合は、6月30日が納付期限となります。
個人事業税
納付期限:8月31日・11月30日の2回で分納
個人事業税は、8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が届きます。基本的には、2回に分けて納付しますが、自治体によっては一括での納税も認められています。一括納付が認められている場合は、8月31日までに納めます。
まとめ
所得税や住民税ばかりに気をとられがちですが、事業が拡大して所得が増えてくると、事業税も課されるようになります。事業税が課されるのは、所得が290万円を超えることがひとつのラインとなっていますので、個人事業主であるなら、事業税の納付書が送られてきても驚かないように、事業税の知識もしっかり念頭に入れておきましょう。
また、課税される場合は、税額を計算して、個人事業税の納付期限に納付できるように手元に納税用の資金を準備しておきましょう。
なお、税理士コンシェルジュの税理士紹介サービス税理士紹介公式サイト-顧客満足NO.1【税理士コンシェルジュ】では、無料で税理士をご紹介しています。事業税など税に関することでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
税理士コンシェルジュは、2008年のサービス開始以来、株式会社タックスコムが運営する「税理士選びの判断基準」を専門にした紹介サービスです。
会計実務の現場経験をもとに、これまで1,000名以上の税理士と面談し、1万件を超える経営者の相談に向き合ってきました。
私たちは、いきなり税理士を紹介するのではなく、「そもそも税理士を変えるべきか」「紹介を使うべき状況かどうか」といった判断の整理からサポートしています。
無料相談を通じて状況を整理したうえで、必要な場合にのみ、条件に合う税理士を厳選してご紹介しています。
▢こんな記事も読まれています
▢一番読まれている記事
- 小計・合計・総計・計・累計の違いって何?正しい使い方をマスターしよう!
- 決算書の「マイナス三角△」の意味とは?具体的な使い方など日本独特の会計事情
- 所得金額と収入金額の違いとは?確定申告で必要な基礎知識と計算方法
- 金融機関お届け印とは?実印と同じ印鑑で兼用しても大丈夫?
- 「棚卸し」とは?意味や目的、作業方法まで分かりやすく解説
- マネーの虎で最も成功した「フランスロール」成功者の波乱万丈な人生のまとめ
- マイナンバーと預貯金口座が紐付けされるとどうなる?
- 「続柄」の正しい読み方・書き方とは?書き方一覧と基礎知識
- 年商とは?売上高との違いや一般的な使い方など年商の基礎知識
- 税理士への苦情・クレームはどこに言えばいいのか?
 税理士コンシェルジュコラム
税理士コンシェルジュコラム



 新着・税理士無料相談
新着・税理士無料相談 新着・口コミ
新着・口コミ