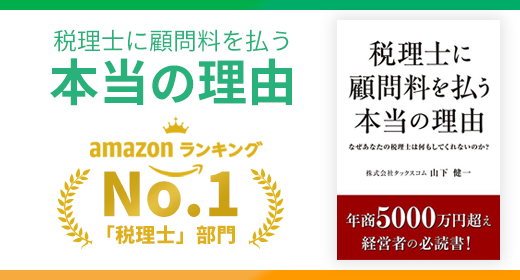税理士との付き合い方に疑問を感じたらチェックしたい4つのポイント
企業経営において、税理士との付き合いは欠かせないものです。したがって、税理士との付き合いに疑問を感じた場合は、その関係性を検討する必要があります。
・税理士に支払う料金について、納得できているか
・その税理士との相性に問題はないか
・経営状態について等、オープンに話せるか
・対等な関係性を築けているか
これらのポイントについて見直し、問題があるようなら解決を図りましょう。税理士との話合いを設けたり、それでも解決しない場合は、税理士の変更も視野に入れることになります。
目次
税理士との付き合いは、面倒?
一般的には、開業するときや、申告時等スポット的な依頼をする際に税理士との付き合いが始まります。また、経営状態が安定してきたタイミングで継続的に税理士と付き合いを始める場合もあるでしょう。
どれくらいの頻度・どの程度のウエイトで仕事を依頼するかは会社によって様々ですが、いずれにせよ税理士を意識するタイミングは、遅かれ早かれ訪れるものです。
税理士と付き合うからには、上手くやっていきたいと思うのは当然のことです。しかし、その付き合いを「面倒」と感じる方も少なくないようです。
たしかに、税理士に仕事を依頼するからには費用が発生するので、コストパフォーマンスも気にしなくてはなりません。また、定期的に顔を合わせることになるので、時間もそれなりに割くことになります。
このように税理士との付き合いについてイメージを膨らませていくと、「税理士と付き合うのは、面倒だな」と感じるのも無理はありません。
しかし、税理士との付き合いでは、ポイントを抑えれば、難しいことも面倒なこともめったに生じるものではありません。税理士との付き合いを、「何だか面倒なもの」から「経営にとってプラスに働くもの」と捉えましょう。
税理士との付き合いは、なぜ面倒に感じるのか
「税理士との付き合いは面倒」と思われがちなのは、「税理士は、どんな仕事をする人なのか」がわかりづらいということが一因です。「その名のとおり、税金についての専門家なのであろう」という、漠然とした印象だけを持っている方は、多いと思います。
また、経営者の方は「税務調査のときに、税理士がいたほうがよいだろう」という情報は持っているでしょう。このような「用心棒」のようなイメージだけを持っている場合、「うちの会社には必要ないか」「困ったときだけ頼ればよいだろう」といった考えにつながるのも無理はありません。
しかし、税理士と良好な関係を築くことは、経営においてとても大切なことです。
「税理士との付き合いは、なんだか面倒そうだ」と漠然としたイメージのまま、税理士との付き合いを放置してしまったり、二の足を踏んでしまったりするのは、経営においてもったいないことといえます。
しかし、やはり「税理士との付き合いって、結局何をするの?」「税理士との付き合いによって、自社の負担が増すのは避けたい」といった不安から、「税理士との付き合いに対するモヤモヤ感がなかなか拭えない」という声も多く聞きます。
税理士との付き合いにおける「モヤモヤ感」解決の最短ルート
「税理士との付き合いは面倒そう」
→だから先延ばししたい
「税理士と付き合ったほうがよいのだろうけれど、イメージが掴めない」
→だから負担が生じることに着手しづらい
このようになるのは「『税理士との付き合い』とは、具体的に何なのか」が曖昧に感じられるからでしょう。
ビジネスにおける「付き合い」ですから、始めたり継続したりするには、会社としても準備や心構えが必要なことは想像に難くありません。面倒だという印象は、無根拠なものではありません。事実、税理士と良好な関係を築くのであれば、会社側にもある程度の体制や、心構えが求められます。
あるいは、すでに顧問税理士がいる場合でも「税理士と、うまく付き合えているのだろうか」「顧問税理士と、どうも上手くいっていない。しかし、税理士を変更したところで、よい変化は望めるだろうか」と悩んでいる場合もあるかもしれません。
この場合、経営者の方が税理士に対して「何を、どこまで相談してよいのか」がわからず、何となくモヤモヤとした気持ちを抱えているという場合が多く見受けられます。
大まかに整理すると、
・税理士との関係はまだ始まっていないが、「税理士との付き合い」のイメージがつかめずにモヤモヤする。
・すでに会社には顧問税理士がいるが、うまく付き合えているのかどうかが判断できず、モヤモヤする。
といったパターンが多いようです。
いずれの場合も、まずは「税理士とはどういう仕事をする人なのか」「自社が税理士に求めることは何なのか」を把握することが大切です。
まだ税理士との付き合いが始まっていないのであれば、自社にとって税理士の提供するサービスが必要か否かを判断する税量になるでしょう。
すでに税理士との付き合いがある場合も、自社のニーズと今の顧問税理士の仕事ぶりが本当にマッチしているのかを検証することができるので、モヤモヤの解消にむけて具体的に動くことができます。
遠回りに感じるかもしれませんが、これが税理士との付き合いにおけるモヤモヤした不安や悩みを解決する最短ルートです。
税理士との付き合いにおける誤解~本当に経営者の味方なのか?
一般的に、税理士は顧問先の企業に対して正しい納税を促すことはもちろん、円滑な税務会計がなされているかを定点観測することにより、経営にとってプラスになるアドバイスや判断材料を提供します。
よりよい選択肢を経営者に提示し、必要以上の税負担や追徴課税といったリスクを未然に防ぐ助言をしようとするので、税理士の発言のなかには、経営者の方にとっては耳の痛い指摘もあるかもしれません。
しかし、それを臆することなく経営者に伝えてくれる税理士という存在は、貴重です。つまり、会社にとっては、円滑な経営の大きな助けとなってくれる味方なのです。
税理士というと「税額を計算し、納税を促される」といったイメージを持ち、まるで税務署のような存在だと考えている方もいるかもしれません。また、「あれこれと、細かいことばかり指摘される」という印象を持っている方もいるでしょう。
端的にいえば「税理士は、経営者の味方なのか?」と疑問を抱く場合もあるということです。しかし、この疑問は総じて誤解によるものです。
たしかに、残念ながら世の中には、「ただ納税額を示すだけ」「意味があるとは思えない指摘ばかりする」といった税理士もいます。
色々と注意され、手間が増え、その効果は感じられないとなれば、税理士との付き合いについて疑問が生じるのも無理はありません。
しかし、大抵の税理士は顧問先企業の味方になる存在です。また、味方になってくれないようならその税理士を選択しない・その税理士との付き合いをやめるという方法もあります。
参考記事:税理士を変更する時の3つの注意点
税理士との付き合いで、おさえたいポイント
税理士との付き合いにおいては、あらかじめ綿密に打ち合わせて決めた内容で契約し、あくまでも対等な立場でお互いに意見をいい合えることが大切です。
そのためにおさえておきたいポイントを、以下に挙げていきます。
税理士との付き合い・ポイント1:相性・相場観も重要
面談をしてみて、話しやすい税理士、相性のよさを感じる税理士を選ぶのがベストです。一方、このように感じるのであれば黄色信号です。
・「どうもウマが合わない」「何だか話しづらい」
↑税理士と顧問契約を結ぶと、定期的に顔を合わすことになります。自分が話しやすいと感じる税理士を選ぶことをお薦めします。
・「料金を支払っているのに最低限のことしかやってくれない」「必要性を感じていないサービスにも料金が発生して納得できない」
↑自社が税理士に依頼したいことを整理し、それにはどの程度の料金がかかるのか相場観をつかんでおくとよいでしょう。
「安かろう悪かろう」は世の常です。しかし、顧問料が高いからといって優秀な税理士とも限りません。料金が安いからといって飛びついたり、高額なのだからと闇雲に信頼してしまうのは禁物です。
とはいえ、コストに見合ったサービスを受けられるのか検証することは当然です。自社が税理士に何を求めているのかを把握し、相場をある程度は掴んでおくとよいでしょう。
税理士との付き合い・ポイント2:料金の確認を怠らない
税理士との付き合いで揉めやすいのが、料金に関することです。例えば、以下のような誤解・トラブルはよくみられます。
・ある日突然、顧問料が高くなった!
↑ 売上高に比例して顧問料が上がる、という契約内容を見落としていたという場合があります。
・毎月顧問料を払っているのに、決算料をさらに請求された!
↑ 顧問料と決算料は別である、という契約内容になっていないか確認してみましょう。
このようなことを防ぐためには、契約時に料金に関する内容をよく確認しておくことです。
もちろん、疑問を持った場合には臆さずどんどん確認しましょう。「どのような仕事に、どれくらいの費用が生じるのか」を納得したうえで、付き合っていくことが大切です。
「こんな疑問をぶつけたら、わがままだと思われるだろうか?」「こんな不満は、普通は持たないのだろうか?」などと考えず、積極的に尋ねてみましょう。信頼に足る税理士であれば、顧客の不安解消のために、誠意をもって答えてくれるはずです。
また、もしも不安や不満が募るようだったら、契約内容の変更や、場合によっては顧問税理士の変更という選択肢もあります。
税理士との付き合い・ポイント3:経営状態をオープンにする
会社にとって、税理士は外部の人間です。経営状態等、会社の情報を打ち明けることには不安が伴うでしょう。しかし、税理士には守秘義務がありますので、過剰に心配する必要はありません。
また、税理士との付き合いにおいて、見栄を張ったり、隠しごとをしたりすると、税理士としても適切なアドバイスをすることができなくなります。結果、お互いに不信感を抱くことにも繋がり、よいことはありません。
例えば、このように考える経営者の方もいらっしゃるようです。
・こんなことまで社外の人に話してはまずいだろうか…
↑ 税理士には守秘義務があります。相談に必要な情報は打ち明けましょう。
・仕事の内容が特殊だから、税理士の先生に話してもわかってもらえないだろう…
↑ 業種によって、アドバイスや判断も変わってきます。税理士にも理解を求めましょう。
一度付き合う税理士を決めたら、覚悟を決め、腹を割って経営状態を明かしましょう。そうすることで税理士の知識・経験を自社に提供してもらいやすくなり、経営にとってプラスに働くことに繋がります。
逆にいえば「この税理士には自社の経営状態を打ち明ける気になれない」と感じるようであれば、契約はしないほうがよいですし、すでに契約をしているのであれば変更を検討してもよいでしょう。
税理士との付き合い・ポイント4:対等な関係性を築く
税理士に対しては、相談事があれば積極的に投げかけ、業務上の疑問があれば遠慮なく質問しても問題ありません。ビジネスパートナーとして、対等な立場同士の付き合いでよいのです。
一方、やたらと上から目線の税理士や、説明をおろそかにする税理士とは、無理に付き合う義理もありません。
例えば、以下のような不満はよく耳にするものです。
・説明内容には満足しているが、言葉遣いが気になる…
↑ 顧客として遠慮せず「もう少し丁寧に話してください」「ビジネスなのでお互い礼儀を大切にしましょう」等と伝えても問題ありません。
・税理士の説明が、正直よくわからない…。意味がわからない言葉もある。
↑ わからないまま話が進んでしまうと、大切な判断を誤る可能性があります。専門家ではない人の疑問を知ることは、税理士にとっても学びに繋がります。積極的に尋ねてみましょう。
「先生に、こんなことを質問しては迷惑だろうか」と税理士に対して過剰に配慮したり、「こちらが顧客なのだから、要望にこたえるのは当然だ」と居丈高に出たりすることなく、あくまで対等な立場で付き合うことが良好な関係に繋がります。
こちらの不満や不快感を伝えても解決しないようなら、その税理士との付き合いを見直す段階に入っていると考えてもよいでしょう。
参考記事:税理士が偉そうと感じた時の対処方法とは?
税理士との付き合いで、代替わりが発生した場合
ここまで、税理士との付き合いにおけるポイントを挙げてきましたが、これらポイントをおさえられていたとしても、代替わりにより新たな関係性を構築しなければいけない場合も増えています。
経営者が高齢化し事業承継をしなくてはならないという状況は、どの業界にもみられることですが、税理士業界にも同様です。
多くの会社において2代目・3代目と経営者が引き継がれていくなかで、税理士事務所もまた、いずれは所長からその子どもや事務所に所属している税理士が新たな所長となり、その税理士事務所の経営を続けていくことになります。
ここで税理士事務所に仕事を依頼している顧客側として気になるのは、「新たな所長先生とうまく付き合えるかどうか」「これまで上手くいっていたことが、変わってしまうのではないか」ということです。
例えば、これまでの所長と経営者の方が同世代だったとします。それを背景に、多くを語らずともわかってもらえた、ということもあったのではないでしょうか。
また、時代の空気や業界の常識といったことを、みなまで伝えずともわかってくれた、といった関係を顧問税理士と築いていた経営者の方も少なくはないでしょう。
しかし、代替わりをすれば、これまでの所長よりも若い人が新所長となることが一般的です。そこを不安の種として、「これまでのように良好な関係が、新たな所長先生と築けるだろうか」「また細々と説明しなくてはならないのか」といった不安を抱えている経営者の方も多いです。
代替わりした税理士との付き合いでは、コミュニケーションの変化にも柔軟に
しかし、これは税理士側にとっても同様です。ぼほ、同じような不安を持っているのです。
「良好な関係を築いてきた顧客との関係性が、代替わりによって変わってしまったらどうしよう」という不安は、顧問先を引き継ぐ税理士であれば当然持っているものです。つまり、お互い様なのです。
「不安なのは顧客側だけでない」と頭の片隅に入れておくだけでも、コミュニケーションは変わってくるのではないでしょうか。
代替わりした税理士との付き合いでは、前任者と比較しすぎないことが大切
例えば、税理士は一般に「先生」といわれています。これは社会的な慣習のようなものであって、深い意味はありません。
付き合いのある税理士に敬意と尊敬の念を持っているために「先生」と呼んでいる場合もあれば、「何となくそういうものだから」という場合もあるでしょう。
この慣習を、新しい所長先生が気にしたとします。そして、「私はまだまだ若輩者ですので、先生とは呼ばずに気軽に接してください」と、顧問先の経営者の方に伝えたとします。
その若い所長先生は、自分よりも社会経験が豊富な方への敬意からそのように申し出たのかもしれません。しかし、その申し出への反応は様々でしょう。
「税理士側がそのようにいったのだから」と、より気軽な「さん付け」、はたまた、あだ名で呼ぶような経営者の方もいるかもしれません。一方、これまでと同様に「先生」「所長先生」と呼び続ける経営者の方もいるかもしれません。
この場合、税理士に対して先生という呼称を使わない経営者の方が、ビジネスにおいて礼を失しているというわけではありません。そして、先生という呼称を使う経営者の方が四面四角でドライである、というわけでもありません。
このような税理士とのコミュニケーションにおける悩みは、様々なことについてまわるものです。「先生」という呼称を例に挙げましたが、その限りではありません。打合せのときの上座・下座や、ちょっとした服装や言葉遣いについて等、気にし始めたらきりがないでしょう。
例えば、打ち合わせをするのに支障が出るほどの態度だったり、まったく打ち解けず相談一つできないままだったりといった、仕事に大きく影響することであればともかく、コミニケーションにおける細かい問題については何が正解かということはありません。
「前の先生はこうだったのにな」といった考えが頭をよぎることがあるかもしれませんが、まずは、新しい関係を良好なものにするべく前向きに取り組んでみるとよいでしょう。
また、代替わりによって新たな提案をしてくれる可能性もあります。典型的なのものとしては、デジタル化・オンライン化への移行があります。諸手続の電子化が進められており、各省庁においても今後の方針が示されるようになってきています。
こうした時代の流れに乗って、代替わりした税理士がこれまでのサービスの見直しや、より効率的な会計業務についてアドバイスをしてくれるかもしれません。
参照:国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A
参照:経済産業省ホームページ経済産業省のデジタル・トランスフォーメーション
コミュニケーションの不和は目につきやすくはありますが、すぐに判断するのではなく、長所短所を見極めて付き合いを検討していくとよいでしょう。
代替わりした税理士との付き合いが、上手くいかなかったら…
とはいえ、顧客側としては、税理士事務所の代替わりによって著しい不満を持つようになった場合、選択肢は幾つかあります。
まず、不満を持ったことについては遠慮なく伝えましょう。ただし、その際に「前の先生だったら…」と過去のことを持ち出すか否かは、ケース・バイ・ケースです。
通常であれば、新しい所長先生も先代と同様に、あるいは先代以上に顧問先のために尽力してくれていることでしょう。ビジネスですから、「慣れるまで気長に」という姿勢を保つのには程度問題でしょうが、引き継ぎ時の多少のバタつきは少しの間、大目に見てもよいかもしれません。
一方、何度伝えても改めてくれなかったり、過去の良好の関係を反故にするような仕事ぶりや態度であるようなら考えものです。顧問税理士の変更も考える必要があります。
もちろん、いきなり税理士の変更を申し出るのではなく、改善を求めたりお互いに理解を深めようと努めることが大切です。しかし、それでも埋まらない溝ならば、「あの事務所とは、付き合いも長いことだし」等とダラダラと関係を続けるよりも、より良好な関係を期待できそうな税理士に顧問を変更するのも一考です。
顧問税理士への違和感は、様々なことにふと現れるものです。気になることがあれば、溜め込みすぎないことが大切です。
税理士との付き合いに、違和感を覚えたら?
代替わりの有無に関わらず「これまでは上手くいっていたのに、最近しっくりこない…」といった場合にも注意が必要です。
こうした事態には、意外と気づきにくいものです。「これまでは上手くいっていた」という積み重ねをもとに「気のせいだろう」「少し待てば解決する」等と検討を先延ばしにしがちです。
様々な要素があることも、気づきにくい要因です。自社の経営ステージが変わったのかもしれませんし、担当税理士の仕事への姿勢や状況が変わったのかもしれません。あるいは時代の変化に自社や税理士が戸惑っていることが背景にあるということも考えられます。
例えば、創業期と経営拡大期では税理士に求めるものは変わってくるでしょう。また、事業承継や大規模な設備投資等、会社が抱える大きな問題に対して、従来の税理士がうまく対応できるかどうかはわかりません。
また、税理士の所属する事務所の状況が変化しているのかもしれません。例えば、顧客が非常に増えて、従来と同様にきめ細やかなサービスを提供することが難しくなっているかもしれません。或いは、これまでとは別の分野へのサービス展開に力を入れているのかもしれません。
もちろん、税理士側が「最近忙しくなったので、御社に対してきめ細やかなサービスをこのまま提供することは難しいです」等と打ち明けることはないでしょう。
したがって、税理士の仕事に対してちょっとした違和感やシグナルのようなものを大切にしてほしいと思います。
「何だか腑に落ちない」「よくわからないが、あまり満足できなくなっているかもしれない」といった具体的に言語化できないような違和感を覚えた場合は、放置しないようにしましょう。例えば、メモに書きとめておいたり、翌月にも同じことを感じるかどうかチェックしてみると参考になります。
長い時間をかけて良好な関係を築くことはとても大事ですが、顧客側・税理士側を取り巻く環境は日々刻々と変化していくものです。よって、これまでずっと問題なく対応してくれていた税理士に対して、ふと物足りなくなるということは珍しいことではありません。
変化の中でもなお、良好な関係を築けているのか、あるいは変化に対応しきれておらず見直しが必要なのかは、時折確認するとよいでしょう。
税理士との付き合いは、信頼関係が大切
税理士や弁護士といった「士業」の人は、とかく「先生」等と呼ばれがちです。しかし、税理士は顧客に協力し、会社の経営を助けるのが仕事です。依頼をしてくれる顧客に寄り添う「お客さん本位の仕事」と捉えれば、税理士業はサービス業に近い性質であるといえるでしょう。
顧客側としては、税理士との付き合いを億劫がらずに「税理士は何ができるのか」「自社は税理士に何を求めているのか」を明確にして付き合いを続ければ、適切なサービスを受けることができます。
ですから、良好な関係を築くことが期待できそうな税理士と出会えたら、ぜひ大切にしてください。
一方、今の税理士に疑問を持っているようだったら、契約内容の見直しや顧問税理士の変更も視野に入れ、税理士との付き合いについて改めて検討してみることをお薦めします。
多くの税理士が、会社のために経営者の方の悩みに答え、経営のプラスになるように努めていますが、専門知識を悪用して悪事や不誠実な行為に手を染める税理士もゼロではありません。
また、悪事ではないにしても、節税対策や資金繰りについての考え方などにズレを感じる場合もあるかもしれません。そこには、会社と税理士の相性の問題があります。自社の求めるものを明らかにし、何に不満を感じているかを洗い出してみるのもよいでしょう。
税理士との付き合いにおいて大切なことは、互いを尊重する姿勢と、パートナーとしての信頼です。ぜひ税理士と良好な関係を築き、経営のプラスとしていただければと思います。
税理士コンシェルジュは、2008年のサービス開始以来、株式会社タックスコムが運営する「税理士選びの判断基準」を専門にした紹介サービスです。
会計実務の現場経験をもとに、これまで1,000名以上の税理士と面談し、1万件を超える経営者の相談に向き合ってきました。
私たちは、いきなり税理士を紹介するのではなく、「そもそも税理士を変えるべきか」「紹介を使うべき状況かどうか」といった判断の整理からサポートしています。
無料相談を通じて状況を整理したうえで、必要な場合にのみ、条件に合う税理士を厳選してご紹介しています。
▢こんな記事も読まれています
▢一番読まれている記事
- 小計・合計・総計・計・累計の違いって何?正しい使い方をマスターしよう!
- 決算書の「マイナス三角△」の意味とは?具体的な使い方など日本独特の会計事情
- 所得金額と収入金額の違いとは?確定申告で必要な基礎知識と計算方法
- 金融機関お届け印とは?実印と同じ印鑑で兼用しても大丈夫?
- 「棚卸し」とは?意味や目的、作業方法まで分かりやすく解説
- マネーの虎で最も成功した「フランスロール」成功者の波乱万丈な人生のまとめ
- マイナンバーと預貯金口座が紐付けされるとどうなる?
- 「続柄」の正しい読み方・書き方とは?書き方一覧と基礎知識
- 年商とは?売上高との違いや一般的な使い方など年商の基礎知識
- 税理士への苦情・クレームはどこに言えばいいのか?
 税理士コンシェルジュコラム
税理士コンシェルジュコラム



 新着・税理士無料相談
新着・税理士無料相談 新着・口コミ
新着・口コミ